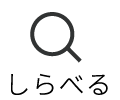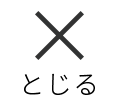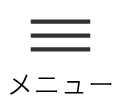2025.07.16
自然の中で、自分たちらしく働くためにIターン就農
“青いレモンの島”で始めた柑橘栽培
佐藤 裕介さん、美和さん/シュガーファーム
農園所在地:愛媛県越智郡上島町 岩城(いわぎ)島
就農年数:5年(2020年独立就農)
生産:レモン・紅まどんな・甘平・サザンイエロー・せとか・丸搾りジュースなど
自然の中で、土とともに、人間らしく暮らしたい
穏やかな瀬戸内海に浮かぶ、“青いレモンの島”として知られる「岩城島」は、愛媛県越智郡上島町を構成する25の島々のひとつ。ここで「シュガーファーム」を営むのが、Iターン農家の佐藤裕介さんと美和さんご夫妻だ。3haの土地を活用し、露地栽培とハウス栽培でレモンや「紅まどんな」をはじめとする、多様な柑橘類を栽培している。
山形県出身の裕介さんと福井県出身の美和さんが出会ったのは、香川県の小豆島だ。野球少年だった裕介さんは、山形から上京後、「野球のように夢中になれるもの」を探すなかで、身体を動かせる仕事として農業の収穫アルバイトを選んだ。小豆島その仕事場のひとつだった。
「最初は長野県でレタス、次に小豆島でオリーブやミカンを収穫しました。その後、沖縄ではバナナ、パイン、マンゴーの収穫もして……。長野で初めてバイトしたときには、もう『農業をやってみたい』という気持ちが芽生えていましたね。朝早く起きて大自然のなかで汗を流し、美味しいものを食べて眠る――そんな人間らしい生活に惹かれたんです」(裕介さん)

一方、福井出身の美和さんは名古屋で就職し、販売や管理業務に従事していた。仕事に打ち込む日々が続いていたが、30歳を迎えたときに「この先、どうやって何をして生きていこう?」と考えるようになったという。子どもを持ちたいという思いもあり、人生を見つめ直そうとしていた頃に本屋で出会ったのが、『土のある暮らし』というコピーが表紙に書かれた雑誌だった。
「雑誌を読んで衝撃を受け、こんな暮らしをしてみたいと、農業フェアなどに足を運ぶようになりました。そこで紹介されたのが、小豆島でのオリーブ・ミカン収穫の短期バイトです。実際に農業に触れてみると、知らないことだらけで本当に楽しくて。いかに効率よく作業できるか自分なりに考えながら働くのも面白かったのですが、それ以上に“他人の評価に振り回されなくていい”という考え方に触れられたことが、大きな収穫だったかもしれません」(美和さん)
農業を営む場所を探す旅へ。支援制度を活用して、たどり着いた岩城島
小豆島で出会った二人は次第に意気投合し、「農業を生業したい」という共通の夢を抱いて「どこで何を育てるか」を探す旅に出た。
「小豆島の景色や環境が本当に素敵だったので、まず頭に浮かんだのが瀬戸内海の周辺でした。尾道を出発して山口、九州へ行き、最後に四国をぐるっと一周。2〜3カ月かけて土地を探しながら、各地を巡りました。訪れる先々で市役所や役場に立ち寄って、補助金の有無や制度の内容、その土地の特産品などを聞いて回りました」(裕介さん)
各地でよく勧められたのは、ミニトマトやイチゴといった果菜栽培だった。Iターンでは広い土地を確保するのが難しいため、小面積でも収穫率の高い作物を推奨されることが多かった。それでも、二人が選んだのは柑橘だった。
「柑橘栽培は重労働で、樹が育つまでに時間がかかり、無収益な期間も長く、確かに新規参入は大変です。でも手をかければかけるほど樹に愛着がわいてくる。小さな苗木を育てていく過程は、まるで高い山を一歩ずつ登っていく登山のような感覚で、そこに魅力を感じたんです」と裕介さん。
美和さんも、小豆島で経験したミカンの収穫が「本当に好きだったので、それ以外は考えられなかった」と振り返る。

岩城島との出会いは偶然だった。旅の途中で「岩城島という島が、レモンや柑橘の栽培がとても盛んだ」と聞いた。そこで二人は岩城島がある上島町のワーキングホリデー制度を活用し、1週間、農業と島の暮らしを体験。ちょうど“天女の羽衣”と称される三千本の桜が見頃で、「島内にある積善山(せきぜんざん)の頂上からの眺めが本当に素晴らしく、圧倒されました」と口をそろえる。
同じく柑橘の産地として知られる愛媛県の別の土地でも研修を受けたが、最終的には、住みやすさや出荷体制、環境などを総合的に判断して岩城島に移住を決めたという。
美和さんにとって大きな後押しとなったのは、京都から移住して15年になるという先輩柑橘農家が、生き生きと働きながら子育てをする姿だった。「この島で、こうやって暮らして、子どもを育てていけるんだ」とリアルにイメージが湧いたという。先輩も熱心に誘ってくれたそうだ。
岩城島への移住が決まったあとは、町が実施している2年間の準備制度を活用。期間中は、町が立ててくれたスケジュールに沿って島内のさまざまな農家の指導を受けた。移住のきっかけをくれた先輩も研修先の一つで、「今後、あなたたちの宝になるから」とハウスの建設や解体のノウハウを丁寧に指導してくれた。アドバイスに従い裕介さんはこの期間で、油圧ショベル(ユンボ)の免許も取得している。

研修中には先輩の力添えで、使われなくなったハウスを解体・再利用して、自分たちのハウスも建設することができた。かかった経費は20万円程度で、「今、同様のハウスを新築すれば1,000万円以上かかるなか、中古のハウスに出会って再利用できたのは本当に幸運だった」と裕介さんは言う。
また、研修期間中には、研修先農家とのつながりを駆使して土地探しも積極的に進めた。そして幸運にも、成熟した果樹のある成木園を借りることができた。露地での果樹栽培は安定するまでには5年ほどかかるといわれるからこそ、「これは大きなアドバンテージだった」と裕介さんは振り返る。
2年の研修を終え、2020年に二人は無事に就農。スタート時には、借りていた成木園での柑橘の栽培を始め、お手製のハウスに植えるための柑橘の苗木づくりも始めていた。そして、苗木が育つまでの間、ハウスではトマトづくりもスタートしていた。
とはいえ、すぐに収入が安定するわけではない。就農後は、国の農業次世代人材投資資金(経営開始型)を利用。さらに、就農時期がコロナ禍であったことから、コロナ禍の持続化給付金なども活用して灌水設備の設置を進めるなど、毎年少しずつ農業基盤を固めていった。
販売は、地域の直売所やECサイトを活用。
写真のひと工夫で「紅まどんな」の注文が前年比4倍に
現在の年間収穫量は、「紅まどんな」が4〜5t、レモンは9〜10tを誇る。初年度は100万円ほどだった売り上げも、5年目の2024年には1,000万円に到達。そのうち約7割が生果、残り3割がジュースなどの加工品として販売されている。現在は農薬量を減らした“特別栽培”にも取り組んでいるそうだ。

販路は多岐にわたる。ふるさと納税や食べチョク、ポケットマルシェなどのECサイトのほか、道の駅や飲食店、JAの直売所にも出荷。なかでも「ふるさと納税で、生果の売上が飛躍的に伸びた」と美和さんは語る。特に「紅まどんな」は、2024年には前年比の4倍となる800件ほどの注文が入ったという。
「ECサイトは、どの商品がどんな理由で選ばれたのかが見えにくく、難しさもあります。それでも、『紅まどんな』の写真にカットした断面を入れてみたところ、注文が急増したのが分かりました。特別栽培に挑戦しているのも、消費者に“何が刺さるか”を考えた結果です。今後も商品そのものや魅せ方、表現を少しずつブラッシュアップしていきたいと思います」(美和さん)
個人運営のECサイトは、手数料はかからないものの、顧客対応の煩雑さから現時点では利用していない。
「大手ECサイトへの出品には手数料こそかかりますが、用意された配送ラベルを箱に貼り、発送するだけですから、とても助かります」と美和さん。
「山と海と柑橘」をテーマにしたファームのロゴをラベリングした「丸絞りジュース」もECサイトを通じて販売中。加えて最近では、島内マルシェやイベントにも積極的に出店。少しずつ認知が広がり、広告効果などの手応えを感じ始めているという。
無理なく、楽しく、地域とともに。二人が描くこれからの夢
今後の目標を聞くと、「いつかは加工場を作りたい」との答えが返ってきた。ジャムやドライフルーツ、冷凍商品など、多様な加工品の製造を見据えた展望だ。ただし、夫婦ともに大規模な法人化や急成長を求めているわけではない。
「ECサイトのアワードに挑戦するなど、ちょっとした楽しみを見つけながら、無理のない範囲で農業を続けていく。そのなかでできるチャレンジがあればし続けていく――。それが、私たちには丁度いいんです」と裕介さん。
これに対し、美和さんも「仕事に追われすぎず、楽しみながら農業を続け、自然のなかで子どもとの時間を大切にしながら暮らしていきたいですね。理想として描いていた“土のある暮らし”からはまだ遠いかもしれませんが、客観的に見れば、私たちも自分たちらしく、幸せな暮らしができているのかもしれない」と微笑んだ。

一方で、過疎と高齢化が進む岩城島に対して、「自分たちにできることはないか」という強い思いを抱く二人。裕介さんは「農業の担い手がおらず、耕作放棄地が広がっていくのは悲しい。自分ができることを続けるなかで、人を雇うなどして、そういった土地も活用できるようになりたい」と語った。
美和さんも「地域に根差し、地域の役に立つ活動に取り組みたい」と、すでに子ども食堂の運営に関わり、子どもたちを招いて「紅まどんな」や野菜の収穫体験などを行っている。「こうした活動のなかで子どもたちが地域の産業などと触れ合う機会を増やし、『上島町や岩城島って、すごくいいところなんだ』と感じてもらえるようにしたい」と二人は語った。
「趣味は農業」と言い切る裕介さんの頭の中には、植えてみたい作物がまだまだある。栗や桃、ブルーベリー、イチジクなどで、すでに挑戦しているものもあるが、その背景には地域への強い思いがある。
「もしかすると、新しい作物を産地化できるかもしれない。柑橘は重労働でもあるため、女性ひとりでやるのは難しいが、女性ができる農業もある。それを示すことで地域への移住誘致につなげたい」(裕介さん)
たどり着いたレモンの島で、柑橘と子ども達のふるさとを守り続けようと奮闘する若い二人。今後の挑戦に、ますます期待が寄せられている。

就農を考えている人へのメッセージ
「農業のスタイルは人それぞれ、『自分がどんな農業をしたいのか』を明確にすることが大切で、それによって、選ぶべき土地も進め方も自然と決まってきます。Iターンならしっかり選ぶことができる。だからこそ、ある程度の覚悟も必要ですね。自然相手の農業は、思い通りにいかないことが大半で、隣の畑が青く見えることもあります。でも、焦らず一歩ずつ進めば、きっと結果はついてきますよ」(裕介さん)
「先輩農家の働き方や子育ての様子を見て、『ここならやっていける』と納得し、この場所を選びました。スタート前にしっかりと準備ができれば、あとはやるだけ。がんばってくださいね」(美和さん)