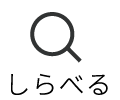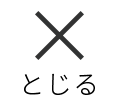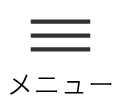2025.09.25
冷や汗よりも、大汗をかきたい。
未経験から始めた“儲かるトマト農業”
小西良和さん/あぐりの和
農園所在地:岐阜県下呂市
就農年数:7年目 2019年就農
生産:飛騨トマト
下呂の風土が育む甘いトマト
岐阜県下呂市で、ハウス栽培によるトマト農園を営む小西良和さん。大阪からのIターン移住で、農業未経験からのスタート。現在は夫婦で45アールの農地を管理し、夏秋トマトを栽培している。昼夜の寒暖差を活かした高糖度の「飛騨トマト」として、農協を中心に出荷。売上は右肩上がりで、いまは法人化に向けて準備を進めている。就農7年目の小西さんに、未経験から農業を軌道に乗せるまでのリアルストーリーを聞いた。

教員志望が農業に転身した理由
小西さんが農業を志したのは、大学4年生の時。教育学部で教員免許を取得し、就職活動をしていたが、多汗症が原因で人と接する仕事に就くことに不安を感じていた。そんな時に目にしたのが、農業インターンのチラシ。それまで農業を身近に感じたことはなかったが、興味を持って参加。奈良県の農家で1週間の体験をしたことで、農業の面白さに気づいたという。
「大学に行かせてくれた両親には申し訳ない気もしましたが、『自分がやりたいことをやればいい』と背中を押してくれました。今では定年を迎えた両親も下呂市に移り住んで、農作業を手伝ってくれています」
全国のトマト産地を巡り、下呂市に移住・就農

就農を決意した小西さんは、大阪で開かれた農業人フェア(就農相談会)に参加。そこで「トマトは儲かる」という話を聞き、栽培品目をトマトに決めた。九州から北海道まで、全国のトマト産地を巡り、新規就農できる場所を探した。しかしながら、就農地探しは思うように進まなかったと、小西さんは振り返る。
「市役所の農政課で話を聞いても、社会経験も資金もない学生に農業が務まるのかと半信半疑で、歓迎されないこともありました。それでも諦めずに探し続けて、最終的に出会ったのが、岐阜県下呂市でした。職員の方が温かく迎えてくれたことや、市の手厚い支援制度に魅力を感じて移住を決意しました」
研修先で出会った師匠と、人生のパートナー
小西さんは下呂市が用意した住宅に住みながら、トマト農家で2年間の農業研修を受けた。研修先では、ハウスの建て方や実践的な栽培技術、農業経営のノウハウなどを幅広く学んだ。
「研修先の農園は規模が大きく、パートさんもたくさん雇っていました。ある時、師匠が通帳を見せてくれたのですが、5日ごとに出荷先から振り込まれる金額を見て驚きました。農業は夢のある仕事やなと(笑)」
研修中に師匠のつながりで45アールの農地が見つかり、国と市の助成制度を活用してハウスを建設。半額の補助を受け、残りの半額は5年間かけて返済した。さらに、新規就農者向けの給付金として、国から年間150万円、下呂市からも50万円の支援を受けた。

就農後は、同じ研修先で一緒に学んだ女性と結婚し、夫婦で農園を営むことに。県外から移り住んで農業を始めた小西さん夫婦にとって、地域に溶け込むことに苦労はなかったのか?
「祖父が地方で漁師をしていたので、なんとなく農村の習慣は理解していました。初めは少し入りにくい印象はありましたが、日常的にあいさつをしたり、草刈りなどの地域活動に参加したりする中で、自然に溶け込めました」
失敗を糧に収量アップを実現
いまでこそ安定した収量を確保している小西さんだが、初めから順風満帆というわけではなかった。借りた農地は研修先とは土質が異なり、肥料や水やりの加減が分からず、1年目は思ったほどの収量を得られなかった。その失敗を教訓に、2年目からは土質に合わせた栽培とカビの原因になる花柄の除去に取り組むことで、病気予防と収量アップに成功した。
「大切なのは、管理に手を抜かないこと。農業は自分がやった分だけ結果に現れるから面白いんです。それが収入にも直結するので、やりがいがあります。夏場はハウス内の温度が50度を超える日もありますが、農作業が苦になることはありません。『早く明日にならないかな~』と思うほど、毎日の作業が楽しいんです。トマトが鈴なりになっているのを見ると、うれしくなりますね」

小西さんが栽培しているトマトは「麗月」という品種で、皮が硬く日持ちするのが特徴。研修先の農園では皮が軟らかい「桃太郎」を栽培していたが、「麗月」の方が作りやすいことから、現在は全量を「麗月」に切り替えた。出荷時期は7月から11月にかけてで、シーズン中は大忙し。また、初めは苗を購入して栽培していたが、段階を踏んで現在は種からの栽培を実践。育苗は簡単ではないが、大きなコスト減につながっている。
法人化と冬場栽培で経営強化へ
現在は、ほぼ全量を農協に出荷。一部は下呂市内のホテルや無人販売所、友人を通して地元・大阪への直売も行っている。一昨年に売上目標の1千万円も超え、税理士とも相談し、法人化することを決めた。今後の規模拡大も考え、あらたな出荷先を検討中だ。来月からは名古屋の仲卸業者への出荷を開始する。出荷の際の手間は増えるが、利益率が高く、経営の安定につながると考えたからだ。
また、年間を通しての収入の安定化を図るため、来年からは新たに70アールの農地を借り、暖房設備を導入して冬場の栽培にも挑戦。ハウス資材の価格は、就農当時に比べて高騰しているが、離農する農家から部材を集め、自分で建てることでコストを抑える。
雇用面では、就農3年目から地域住民をパートタイムで雇用。出退勤自由のルールで、保育園の送迎などにも柔軟に対応している。
「働きやすい農園と言ってもらえるのはうれしいですね。冬場も出荷するようになれば、通年でパートさんたちを雇用できるようになります。そうすれば、安心して長く働いてもらえるかと。とにかく人手が必要なので、たくさんの人に来てほしいです」

若手の育成で地域への恩返し
農業を始めてから、自身の考え方にも変化があったという。
「最初の年は100点を目指していたら、空振って失敗。師匠が『しゃあない』とよく言っていて、7、8割の出来で十分と思えるようになりました。野菜は水をやれば育つ。それほど神経質にならなくていいと分かってからは、自分を追い込まずに大きく構えられるようになりました」
農業研修を終えて7年経ったいまでも、師匠や研修仲間との交流は続いている。ときどき集まっては一緒にお酒を飲みながら、情報交換をしたり、コミュニケーションをとったりして、つながりを保っている。また、小西さんのように岐阜県に移住して、あらたに農業を始める人も増えてきているという。
今後の展望を聞くと、「お金持ちになりたいです!」と、屈託なく答える小西さん。でもそれ以上に、地域に恩返ししたいという思いがあるようだ。
「これまでのいろいろな出会いがあって、いまの自分があります。農業未経験の僕を受け入れてくれた下呂市や農家さんには、とても感謝しています。師匠は損得勘定抜きで、何も知識がない僕に、農業のことを一から教えてくれました。いつかはうちの農園でも研修生を受け入れて、地域の農業を担う若手の育成に貢献したいと思っています。そうすることで、下呂市をもっとにぎやかにしたいです」

就農を考えている人へのメッセージ
「農業は手をかけた分だけ返ってくる一方で、甘えるとそれが結果に出てしまう厳しさもあります。そのため、『美味しいトマトをつくる』『売上を増やしたい』など、自分なりの目標ややりがいを持って取り組むことが大切です。また、他の農家とのコミュニケーションを通じて栽培の工夫や考え方を学ぶことも欠かせません。どの地域で就農するかは人によって相性があります。視野を広げて、自分に合った場所を見つけることが、農業を長く続けるための第一歩だと思います」