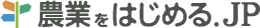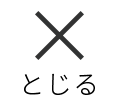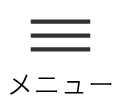2024.02.15
移住先の雪国で継承したウコン栽培
加工品の開発でウコンの魅力を伝える
田中 美央さん・斉藤 翔さん/カズイチウコン
農園所在地:新潟県三条市
就農年数:4年目 2020年就農
生産:ウコン、加工品
新潟県の真ん中に位置する三条市。その東部にある下田(しただ)地域は、冬になると2メートル近くもの雪が降り積もる豪雪地帯。そこでインド原産のウコンを栽培しているのが、田中美央さんと斉藤翔さんだ。現在は「カズイチウコン」の屋号で、復業としてウコンの栽培と加工品の販売を手掛けている。
地域おこし協力隊員時代に出会ったウコン栽培の師匠

田中美央さんは新潟市出身。4年間勤めた旅行会社を退職後、世界一周の旅に出た。帰国後は広告会社勤務を経て、三条市の地域おこし協力隊に着任。2016年、協力隊の活動中に取材で訪れたのが、下田地域で農業を営む故・山崎一一(かずいち)さんだった。当時、90歳近い年齢でありながら、30年以上にわたってウコン栽培を一人続けていた。田中さんは、山崎さんのことを次のように振り返る。
「一一(かずいち)さんの第一印象は『優しいおじいちゃん』。ウコンのことを聞くと楽しそうにいろいろ教えてくれて、ウコンへの愛情が伝わってきました。なんでもやってみようという方で、他にも珍しい作物を育てていました。外から来た私たちを受け入れてくれたのも、そんな性分だったからかもしれません。一一(かずいち)さんは1989年に沖縄からウコンの種イモを手に入れて栽培を始めました。自身で栽培方法を確立して、栄養繁殖で種イモをつないできたのです」

「一一(かずいち)さんの家に行くと、いつもたくさんお茶を入れてくれて。一緒にテレビで相撲を見たりもしましたね。そんな何気ない日常が思い出に残っています」
そう話すのは、田中さんと一緒に農園を運営する斉藤翔さん。斉藤さんは青森県出身のデザイナーだ。先に隊員として活動していた田中さんの元を訪れた縁で、その後、三条市の地域おこし協力隊となった。当時は、農家として起業する考えはなかった二人だが、山崎さんから分けてもらったウコンの種イモを植えて栽培するうちに、作物としてのウコンの魅力をもっと広めたいと考えるようになった。山崎さんの畑を手伝いながら栽培技術を学び、ウコンの生産をなりわいとすることに決めた。

ウコン栽培はトライアンドエラーの繰り返し
カズイチウコンでは、借りている畑で春ウコンと秋ウコンの2品種をそれぞれ300株ずつ栽培している。春と秋の名が付く品種だが、どちらも例年の4月から6月に植えて11月頃に収穫する。その一部を種イモとして屋内で保管し、11月から2月まで休眠。3月頃に目覚めさせ、初期生育を行う。暖かくなると露地に定植し、これを毎年繰り返している。インド原産の植物だが、冬の寒さが厳しい新潟県での栽培は難しくないのだろうか?
「ウコンは耐寒性のない植物なので、0度以下の環境に置くと枯れてしまいます。また、保管時にはカビを生やさないように注意する必要があります。その2点だけ気を付ければ、栽培自体はそれほど難しくありません。とても生命力の強い植物で、病気にもならず、獣害もありません。放っておいても枯れませんが、収量を上げ、質の良い物を作るには、それなりに手入れが必要です」(斉藤さん)

耕作から収穫までの一連の流れを手作業で行う。ウコンは一つの株でおよそ1キロの重さがある。600株を収穫するとなれば一苦労だ。さらに収穫後の根切りも重労働だという。
「いまだに私たちもウコン栽培で何が正解なのか分かっていません。年に1度しか試せないので、毎年トライアンドエラーの繰り返しです。例えば、マルチングをしたりしなかったり、肥料を変えてみたり。経験値は増えていきますが、必ずしも年々収量が上がっているわけでもありません。一昨年はたくさん収穫できましたが、昨年は収量が少なかった。天候の影響が大きいですが、きっとそれ以外にも要因があるはずです」(田中さん)
事業計画書通りには進まない農業経営
田中さんと斉藤さんは、山崎さんの種イモを継承し、自家栽培のウコンを使った加工品販売を手掛ける会社を2020年に設立。法人化に先駆けて、加工品の開発に取り組んだ。二人が考えたのは、ウコンを含む数十種類の薬草を使ったノンアルコールシロップ。商品化にはクラウドファンディングを利用し、160人以上の支援を得て実現した。幸先の良いスタートだったが、二人はモヤモヤとした気持ちでいた。
「当時はうまく言語化できませんでしたが、ウコンの香りを引き出し切れなかったこと、また、ウコンそのものの魅力よりも地域おこしの取り組みとして評価されることに違和感があったように思います。また、見返りを求めずに手伝ってくれる方もいましたが、ありがたい気持ちと同時に何も還元できない心苦しさがありました」(田中さん)

ノンアルコールシロップに続いて、ウコン茶、ウコンパウダー、タブレット、ウコン染レザー製品なども商品化したが、「これだ」という手応えがなかった。事業計画書は作ったものの、実際にはその通りにはいかずギリギリの状態が続いたという。原点に返り身の丈に合った農業経営にシフトするために、2023年に法人を解散。現在は二人とも違う仕事を持ちながら、復業としてウコン栽培を続けている。別の職を得ることで生活は安定したが、兼業ゆえの難しさも感じている。
「農作業は基本的に勤め先から帰った後か週末。いざ作業をしようと思っても、ちょうど雨に降られることもあります。お金は管理できますが、天気だけはどうにもなりません」(斉藤さん)
あえて分業にはせずに、栽培から商品企画、販売、経理までを二人で協力しながら行う。休日や忙しい時期がそれぞれ異なることから、お互いに連絡を取り合いながらカバーし合っている。
「一人では行き詰まってしまうことも二人いれば相談し合える。かといって人数が多くなれば統率が難しくなるかもしれません。二人であれば、すぐに決められてスピード感を持って取り組めるのは良いところです」(田中さん)
「健康食品」としてのウコンのイメージを変える

栽培や経営もさることながら、それ以上に苦労したのはウコンのイメージを変えることだった。日本では「ウコン=健康食品」のイメージが強く、嗜好品としての認識はない。ウコンそのものの魅力を知ってもらうためにはどうしたらよいのか。そう考えて取り組んだのが「ウコンチャイ」の商品化だった。レシピ開発には専門家の力を借り、製造は加工業者に委託。ウコンならではの香りを引き出した商品が完成した。
「自信を持ってウコンの魅力を伝えられる商品です。ようやく自分たちが目指していたものがかたちになりました。『体にいい』とか『地域おこし』とか、そうした文脈ではなく、『おいしい!』と商品そのものを気に入って購入してくれているのがうれしいです。定番商品として息の長いものにしたいですね」(斉藤さん)
販売先は、新潟県内外の飲食店など約10店舗。その中には以前クラウドファンディングでつながった店もある。レシピ開発者の紹介などもあり、少しずつ取り扱い店が増えている。

カズイチウコンのこれから
さまざまな試行錯誤を経て、新たな段階へと進んだ田中さんと斉藤さん。そんな二人に、カズイチウコンの今後の展望を聞いた。
「人から『何を育てているの?』と聞かれて、『ウコン』と答えると、そこからコミュニケーションが広がります。ウコンについて説明するのは難しいのですが、それもまた楽しいです。ウコン栽培には答えがないから面白い。一一さんから受け継いだ種を絶やさずに、これからも作り続けていきたいですね」(田中さん)
「社会的成功とかではなく楽しく続けていられれば100点。必ずしも売れなければ不幸というわけではありません。今後も事業を継続していくために、加工品を作って流通するという基本路線に立ちながら、たくさんの人にウコンの魅力を伝えていきたいです」(斉藤さん)

一人の農家の好奇心から始まった雪国でのウコン栽培は、外から来た二人の若者を引き合わせ、その種は引き継がれた。結果を出すことだけが目的ではなく、その過程自体を楽しんでいる二人に気負いは感じられない。農業をなりわいとして続けていくには、もちろんお金が必要だ。しかし自分たちが育てている作物への愛情や作る楽しみがなければ農業は続かないかもしれない。気の合う仲間とウコンを作る楽しさ、それこそが二人の原点なのだろう。

就農を考えている人へのメッセージ
「就農してからミスマッチが無いように、まずは自分がどんな農業を志向するのかを考えると良いと思います。大規模で収益性の高い農業なのか、身の丈に合ったニッチな農業なのか。それによって出会う人や揃える道具も変わってきます。人それぞれ正解は違います。初めに方向性が決まると、その後の指針になるはずです」